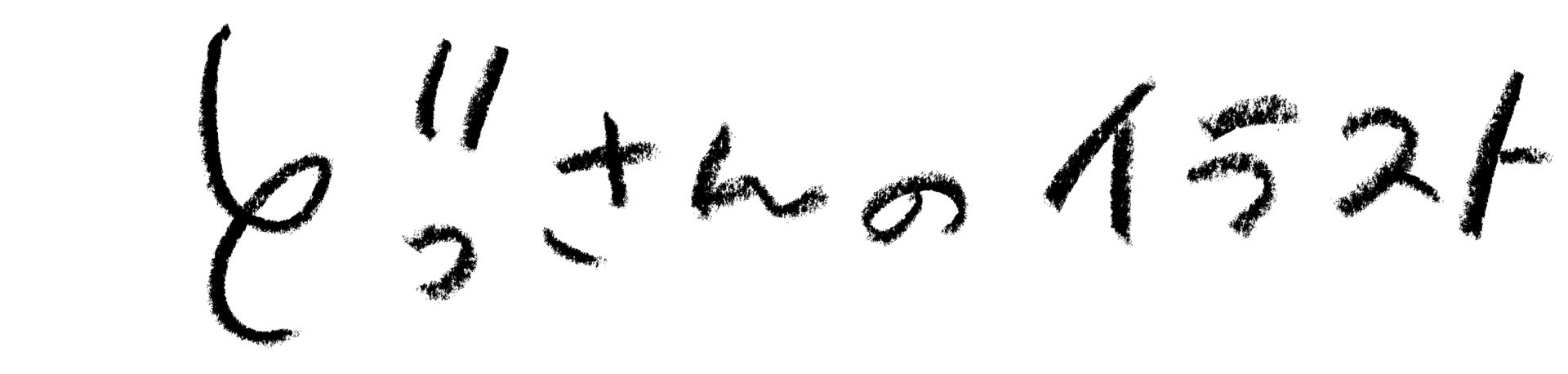小農のむずむず
元旦に起きた地震から、早2ケ月が過ぎようとしている。
生活苦は何にも変わってないしそこまで前向きにもなれてはいない。
インスタで被災しながらも被災者を支える活動をしている人、
新聞で復興に立ち上がっている人を見るとすごく焦ってしまう。
仕事も再開したいし、地震についてのあれこれを絵にしたい。
それでもこの2月はライフワークの千枚田のことで頭がいっぱいだ。
安否不明者、生活再建、まだまだ命を繋ぐ支援が足りてない中で
時期尚早だったかもしれないが、2月6日から千枚田修復の資金を募るため、
愛耕会でクラウドファンディングを始めた。
愛耕会で、とはいえ言い出しっぺは私と愛耕会会長に就任したばかりの旦那。
見切り発車だったので愛耕会の他のメンバーが賛同してくれるか不安だった。
メンバー1人1人に電話して、資金集めはなんとかするから
また一緒に田んぼ直したり米作りできるように活動しましょう、と伝えた。
その中の一人、主要メンバーのおっちゃんが
「俺はもう田んぼも畑もやめる。もう愛耕会も辞める」と言い放つ。
旦那が電話したのだが、とてもイライラしている様子だったと。
私はどうしてもその人のことが気になり、その人と同じ避難所にいる母に電話して様子を伺った。
「あの人、ふさぎ込んでしまって相当落ち込んでいるよ。
避難所でのストレスや、家も潰れてこの先の住む場所も決まってない」。
能登の人は都会の人と違って、生活の基盤を変えるということがとても難しい。
家の周りの自然のことを熟知して、山の恵みをいただいたり、
田んぼや、畑や、そこに営みがあって、そこで生きること、そこに居ることが
その人のアイデンティティそのものだったりする。
それを失ってしまうことはどれだけのことなのだろうかと考える。
そのおっちゃんもまさしくそうで、仏頂面でシャイな能登の男でありながら、
田んぼを一人で黙々とする姿がかっこよかったり、
強面だけど意外にも盆栽が趣味で、その繊細さにギャップを感じたり、
言葉で伝えるのが苦手な代わりに山からたんまりと山菜を採ってきて惜しげもなくくれたり、
自然とともにその人が形作られている。
家や納屋や農業機械が全て破壊され、能登にも住めなくなって、
金沢の色のないただ息をするだけの避難所に押し込まれている。
そんな投げやりの気持ちになっても当たり前だ。
能登には、商売ほどは多くはないけど、
自分の家族に食べさせるには多すぎるほどの作物を作る
プロフェッショナルな「小農」がたくさんいる。
それが能登のいいところだし、それがこの能登を創ってきた。
食べるものが豊かにあることが、きっと心の豊かさにも繋がって
「能登はやさしや土までも」という言葉も生まれたのではないかと思う。
この地震で、愛すべき小農は確実に減るだろう。
そんなニュースも多く目にする。
でも、今は冬。
春が近づいたら、小農の血が騒いでむずむずして山や畑に行きたくならないだろうか。
自然のスケジュールに合わせて生きてきた人たちだから、きっとじっとしていられないはず。
そうなったら、また、田んぼに誘おう。
今はまだ時期尚早。
今しばらくは、むずむず、を期待して待つ。